よくわからないのに、なぜかずっと気になってしまう。
そんなものたちが、ふと気づけば、そばに残っている。
一生モノというのは、
あとから「そうだった」と思うような、時間の中で育っていく何かかもしれない。
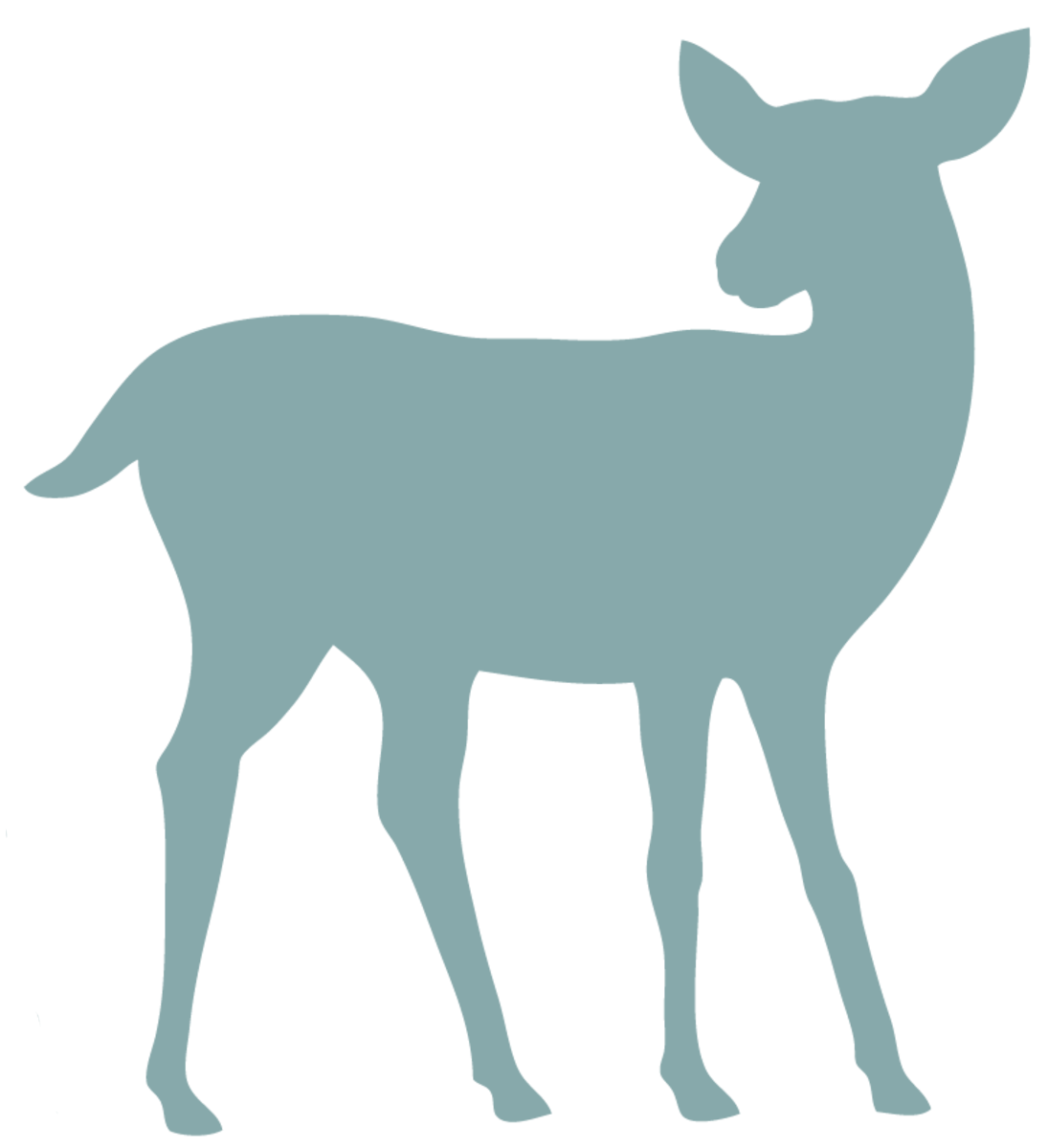
仮面しか見ることのできない人間に災いあれ。背後に隠れているものだけを見る人間に災いあれ。
真のビジョンをもつ人間だけが、たった一瞬の間に美しい仮面とその背後の恐ろしい顔を同時に見る。
その額の背後にこの仮面と顔を、自然にはいまだ知られぬかたちで統合するものは幸いである。
そんな人間だけが生と死の二重の笛を威厳をもって吹くことができるのである。
ある占星術の本のなかに、抜粋されていた言葉。
なんとなく言っていることの雰囲気は感じられるのに、
何度じっくり読んでも、すっと理解できるわけではない。
けれど、「むずかしくて何を言ってるかよくわからない」で終わらせられない離れの悪いものは、きっと今の自分に響いているのだろう。
だからこそ、何度も見返したくなる。
あのとき心に引っかかった余韻に、また触れたくなる。
気づけば惹かれてしまう、「抽象さ」

時代を越えて、ながく愛されてきたものがある。
たとえば『星の王子さま』や『銀河鉄道の夜』、ピカソの『ゲルニカ』。
どれも、最初はすこし難しく感じることがある。
抽象的なものが多いのだ。
しかし、その「抽象さ」があるからこそ、
受け手に自由を委ねてくれている。
誰がどう受け取ってもいい。
どの時間を生きる人にとっても、自分なりの意味を見つけられる。
だからこそ、長く愛され続けているのだと思う。
難解、または、柔軟さ。『星の王子さま』という一冊

『星の王子さま』は、読むたびに表情が変わる本。
中学生のとき、社会人になってから、そして今。
読みタイミングで、まったく違う印象を受ける。
作品は同じでも、解釈が変わる。
そして、その解釈を通して、自分の変化を感じられる。
それはきっと、最大の娯楽でもあるのだと思う。
わたしの手元には、何冊かの『星の王子さま』がある。
そのうちの一冊は、小学生のときに母に買ってもらったものだ。
当時は、ふわふわしていて掴みどころのない物語に思えて、
正直よくわからなかった。
けれど、大人になった今、読み返してみると
その深さに惹き込まれて、何度もページを開いてしまうのだ。
読むたびに違う感覚を味わえるたのしさが、ようやくわかってきた気がして。
今では、手放せない一冊になった。
(ちなみに、池澤夏樹さんの訳が好きです)
一生モノは、「なんとなく在る」で、じゅうぶん

“一生モノ”と呼ばれるものって、
その瞬間に自分と完璧に合っていなくても、
あとになってから、その価値に気づくことがある。
時間と経験を経て、「あのときはわからなかったもの」が
すこしずつ輪郭を帯びて、心の中に居場所を持ちはじめる。
それはきっと、「価値が育つ」ということなのだ。
たとえば、革の経年変化のように。
だから、必ずしも「今が100% 完璧!」じゃなくていい。
知り尽くしていなくてもいい。
抽象的でも、曖昧でも。
なんとなく「そこに在る」ことが、
一生モノになる理由は十分にある。
たとえ、それがほんの偶然の出会いだったとしても。
そう思うと、
今なんとなく大切にしているモノやコトが、
もっと愛おしく感じられてくる。
もしかしたらそれは、
これからの人生を共に歩んでいく相棒かもしれない。
人というのは、きっと、
欠けているところを埋めるようにして、
自分の変化や成長を感じながら、生きているのだろうと思う。

